不登校でも出席扱いされる通信教育といえば「すらら」と言われるほど認知度の高い通信教育。
しかし、すららを受講したからと言って、自動的に出席扱いとなるわけではありません。
学校側と、「登校扱いにしてくれるよう」交渉していく必要があります。
今回は、「すららで不登校を出席扱いに!学校との連携方法を徹底解説|口コミも紹介」と題し、すららで不登校を出席扱いにする方法、学校へのアプローチの仕方を具体的にご紹介します。
一日も早く手続きを進め、「出席扱い」にしてあげたいという皆様に参考にしていただければ光栄です。
まず、大切な結論を2つ先に申し上げます。

すららの資料は交渉の際の一番の武器になるといっても過言ではありません!
下記から、無料ですららの資料請求をできるので、学校側に相談する前にご用意下さい。

今すぐこの制度を活用しないとしても、少しでも興味がある方、気になる方は、無料の資料請求や無料相談をされて、この制度の概要を事前に把握されることをお勧めします。
すららで不登校を出席扱いに!学校との連携方法の手順を解説

では早速、「すららを利用した通信教育」で、「不登校でも出席扱いにするための学校との交渉の仕方」を順を追ってご説明します。
ステップ① 事前準備
そのため、学校との話し合いにはこちら側(保護者)が資料を用意する必要があります。

「すらら」の素晴らしいところは、記事冒頭の流れですららに資料請求すると、その資料がすべてまとめて送られてくるという点です。
【すららで送ってもらえる資料】
- すららの資料パンフレット
すららの教材について、要点などをわかりやすく説明されたパンフレットです。 - 出席扱い制度認定のお願い(依頼書)
学校へ出席扱い制度認定のお願いする依頼書のパターン(雛形)です。出来上がった書式が送られてくるので、学校名・子どもの名前・保護者の署名をして押印するだけ。
口だけの依頼ではなく、書類にすることで格が上がる! - 出席扱いになった前例がわかるもの
ほとんどの学校・教員はこの制度をまだよくわかっていない人が多いです。この資料も役立ちます! - 文部科学省の「不登校児童生徒への支援の在り方について」の通知
ネットから自分で印刷することも可能ですが、こちらも丁寧にそろえて送ってもらえます。何度も言いますが、学校側がこの制度を周知していないことがほとんどです。
文部科学省の通知を提示することで、学校側の態度も変わりやすいんですよ。
出席扱いの条件なども明示されているので、周知知してもらうことで交渉がスムーズにいきます。 - 「ICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出席扱い」についてよくある質問をまとめた資料
実際、出席扱いの細かいルール決めをしていると、いろいろ疑問が出てきます。Q&A方式で事例がのっていますので、学校側・当事者どちらにもとても参考になるのでおすすめ。 - (すでに学習しているなら)学習履歴・ログイン履歴を印刷したもの
こちらは自分で用意するものです。必須ではありませんが、出席扱いのルールを決めるうえでの参考資料になるので、すでにサービス(学習)を始めている方はぜひ用意してください。
すららに資料請求したら、発達障害と不登校のピンポイントの資料が届いた。
そう、欲しいのはこう言うアドバイス。
去年から悩んでたけど、今年はチャレンジすることにした。#不登校
#発達障害
#すらら pic.twitter.com/DdbZy2i7uZ— めめ@3歳児&9歳児 (@meme3674) April 29, 2022

ここまでしてくれるサービスは他にはありません。本当に、不登校児童生徒やその家族に寄り添ってくれたサービスだと感心・感謝の手厚さです。
ステップ② 担任への相談

学校側へのアプローチに進んでいきますが、こちらは順番が大切です。
面談より先に第1番目に担任へ次のように告知しておきましょう。
何度も繰り返しますが、ほとんどの教員がこの制度を周知していません。

私の経験ですが、担任・校長・教頭のみならず、教育委員会の先生方も知りませんでした
突然このような相談をしても、はぐらかしたり、学校長の判断で……。などとにげられることも……。
事前告知することで、担任の先生も「出席扱い制度」について少しは調べてくれたり、相談内容についての心構えをしてくれることを期待しましょう。

もちろんこの段階で、資料をお渡ししていてもいいですね。少しでも目をとおしてくれていれば、理解も早まりますから。
ステップ③ 学校との面談(交渉)日程を決める

最終的に、「学校長が出席扱いが可能かどうか判断する」ということになりますので、なるべくなら学校長を交えた面談を希望しましょう。
突然訪問しても会えないと意味がないので、事前に面談の日程調整をお願いしましょう。

不登校の出席扱いについてのご相談で連絡をいたしました。○年○組の保護者です。
文部科学省のICT教材による自宅学習が出席扱いになる制度があるのはご存じでしょうか?
○○(子供)が学校に再び戻れるよう再登校を目指して、この制度を活用し、ICT教材による自宅学習をしたいと希望しています。
自宅学習を出席扱いとしてもらえることで、子どもの心の負担が軽減し、自己肯定感や学習への意欲も高まります。
本人も自宅学習にやる気を見せています。いずれは、学校に登校できるようになることが目標でありその足掛かりと考えています。
全国的にたくさんの前例もあり、前向きな望みを抱いていますので、ぜひ資料を見ていただきたいと思っています。
最終的な判断をなさる校長先生や教頭先生にも同席していただいたうえで、お話をさせていただきたいのですが、お時間を作っていただけないでしょうか?
特に注意すべきは以下の点です。
- 再登校につなげるための、自己肯定の手段としての自宅学習である点
- 特に中学生の場合は、不登校でも進学に向け内申点をとても気にします。出席扱いできることで進路の可能性を広げてあげることにもつながるので、心理的な重みをだいぶ取り除いてあげることができます。という点
- 不登校を打開し、再登校を目指した前向きなご相談ですという姿勢。

再登校を目指した相談をしたいということを強く訴えましょう。学校側も受け入れやすくなるはずです。
ステップ④ 学校側との面談(交渉)

いよいよ学校側との交渉です。
緊張しますが、「相談」という気持ちで落ち着いて望みましょう。
持ち物(忘れ物がないように!)
- すららの資料パンフレット⇒すらら資料請求はこちらです
- 出席扱い認定制度のお願い(依頼書)
- 出席扱いになった前例がわかるもの
- 文部科学省の通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」を印刷したもの
- 「ICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出席扱い」について、よくある質問をまとめた資料
- (すでに学習しているなら)学習履歴・ログイン履歴を印刷したもの
- すらら担当者の連絡先
- 筆記用具
残念ですが、一度で願いが聞き入れられることはほとんどありません。

学校は古い慣習やしきたりを重んじます。新しいことへの受け入れはとにかく慎重すぎるほど慎重です。
何度か足を運ぶことを覚悟しながら、なるべく穏やかに話を進めていきましょう。
結論が出ないことは想定しておきましょう。必ずいつまで(〇月〇日まで)にご検討くださいと伝えてください。

私はこれを伝え忘れてしまい、学校側からは一切の連絡もないまま、業を煮やしいて二週間後に電話で確認しても、「まだ検討中」だとはぐらかされてしましました。
学校も忙しいので、面倒なことは後回しにされていたのではと腹が立ちましたが、期日を伝えなかった私のミスだと考え、その場で期限を提示しました。
期限を提示することで、アプローチもしやすくなりますよ。
万が一認められなくてもあきらめないでくださいね。
悪いことをお願いしているわけではありません。制度として認められているので、自信をもって何度でも相談を重ねていきましょう。

実は私は、教育委員会にも足を運んでお話をしました。どちらにしても、学校長判断に変わりはありませんが、味方が多いに越したことはありません。すらら担当者の連絡先を教えておくと、出席扱いになった事例などの説明をしてもらえますよ
ステップ⑤ すらら出席扱いに

校長先生が出席扱いを認める判断を下したら、学校との協力・連携体制を具体的に確認しましょう。
確認事項(重要)
- 利用するICT(オンライン)教材
- 出席扱いのルール・確認の仕方
- 学習履歴の提出方法
- 成績のつけかた
- 学習計画(すららコーチに相談)
- 学校との連絡の頻度と、やりとりの仕方
例えば、すららには学習の履歴が自動で記録された上でいつでも管理画面で確認が可能。
本人や保護者はもちろん、校長や担任にもすぐに学習データを提示することができます。
また、学校から1週間に1回登校することが要求される可能性もあります。でも子供によっては1ヶ月に1回の登校でもストレスを感じることもありますので、親・子・学校ともに条件をしっかりと確認していくことが大切ですよ。
成績の付け方についても確認しておくと安心ですね。
文部科学省が定めている「出席扱い制度」とは

文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)令和2年度10月25日」の通知により、ICTで自宅学習が出席扱いできるようになりました。
自宅学習の努力を認めることで、いつかまた学校に行きたいと思ったときのために、学習の遅れを最小限にしておけるよう作られた制度です。
この制度を活用すれば、不登校で学校を休んでいても、家庭学習を出席扱いにして、その先の進路などの選択肢を広げていける可能性があります。
出席扱いの制度を受けるには制度を利用するには、いくつかの条件を満たした上で、在籍する学校と交渉・連携していくことが重要です。。
すららは条件をすべて満たしています。
口コミに見るすららを活用した不登校生の出席扱い認定制度のポイント!

すららを実際に利用した方の口コミを調査することで、すららを活用した不登校生の出席扱い認定制度のポイントを探ってみましょう。
自己肯定感が生まれ学校に復帰のきっかけになった
こういう成果が出るとうれしくなりますね!
https://t.co/bWf8zRbes4— すららネット (@Surala_School) February 18, 2016
不登校が長引くと、特に子供に重くのしかかるのが、「学習の遅れ」問題です。
勇気を出し、学校に行けたとしても、授業の内容が全く分からない状態では登校への精神的ハードルが高くなってしまいます。
すららは、授業に追いつくまでに必要な学習内容、単元数を一目で確認、それを元にお子さまに合わせた学習環境を提供します。分からないところがあるとき質問機能を使えばすららコーチが回答するので、「わからない」をそのままにせずしっかり理解を深められます。
勉強を通してできる!の積み重ね、褒められることの経験がお子さまの自己肯定感をはぐくみます。
中学生の内申点対策(受験対策)
学校復帰を目指す不登校のお子さま、とくに受験を控えたお子さまにとって出席日数が足りないことが不利になってしまうケースが多くあります。
すららで出席扱いできることで、まずは復帰へのきっかけを作れることが大切です。
すららの公式サイトでも、「すららの学習により出席扱いを受け、無事高校に合格された」方の体験談が紹介されています。→「HSPが原因で不登校、すららが出席扱いされて欠席日数ゼロ。高校合格までの道のり。」

我が家の場合も、すららを使用していなかった不登校の時、学校から届いた通知表は判定不可なのか真っ白な状態。娘はその通知表を見てさらに心を痛めたいました。すららで出席扱いになっただけでも、未来に希望を持てた様子でそこから前向きになっており、進学という目標に向かって頑張っています。
すららで不登校を出席扱いに!学校との連携方法を徹底解説|口コミも紹介まとめ
「すららで不登校を出席扱いに!学校との連携方法を徹底解説|口コミも紹介」と題し御紹介いたしました
すららを活用した不登校生の出席扱いの方法を、学校側へのアプローチの仕方とともにナビゲートしてきましたが、いかがでしたか。
すららを不登校の出席扱いにするためには、所属学校長の許可が必要です。
すららは、そのアプローチを公式にサポートしてくれる手厚いサービスを提供してくれるオンライン教材です。
無料資料請求の際に、相談もできるという点も本当に頼りになります。
今すぐこの制度を活用しないとしても、学校側がこの制度を把握していない場合も考えられますので、すららで無料の資料請求や無料相談をされて、親御さん自身この制度の概要を事前に把握されることをお勧めします。
不登校でも出席扱い(文部科学省認定)できる通信教育・オンライン授業6選【不登校支援】




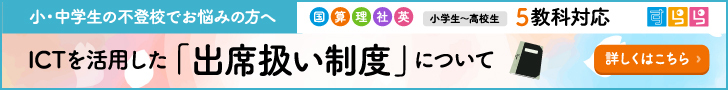
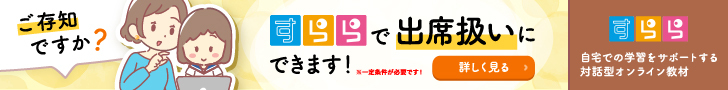

-口コミや選び方を紹介-1-120x68.png)
